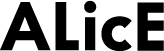#22
人間中心の住宅復興とグリーン・プレイスメイキング

マリ エリザベス 准教授
東北大学災害科学国際研究所 防災実践推進部門
「グリーン・プレイスメイキング」とは、地域の空間を緑豊かに整備し、人々が集い交流できる場を創出する取り組みを指します。こうした活動は、コミュニティの結束を強め、住民の生活の質を高めるとともに、災害復興の過程においても重要な役割を果たします。私は、このグリーン・プレイスメイキングの実践を通じて、被災地復興における新たな可能性を探る研究を行っています。
私と、建築・災害研究との出会い
私はアメリカ・ウィスコンシン州、「大草原の小さな家」の舞台となった田舎で育ちました。幼いころから、ものづくりやデザインといった創造的なことが好きである一方、整然とした数学にも魅力を感じており、その二つを組み合わせることに心を惹かれていました。また、自ら家を設計し建てる人の姿を見て、とても素敵だと思った記憶があります。美しいものだけでなく、建物が立ち上がり、大きな空間が生まれること自体に魅力を感じていたのかもしれません。高校生の頃には、精密さと創造性を兼ね備えた建築という学びに強く惹かれるようになりました。しかし、進学した大学には「建築」という専門分野がなかったため、美術史を専攻することにしました。図書館でさまざまな本を読むうちに東京の街に興味を持ち、日本建築をテーマとした卒業論文を書くに至りました。
大学卒業後の1年間、私は外国青年招致事業(The Japan Exchange and Teaching (JET) Programme)に参加し、横浜の学校で英語を教えました。その後、ワシントン大学建築学科の修士課程に進学。社会問題や困っている人々のための建築に関心があり、建築が人々を支え、社会を改善する手段になればとの思いから、学生時代にはホームレスや低所得者向け住宅について学びました。
2006年、ハリケーン・カトリーナがアメリカ南部に甚大な被害をもたらしました。私はそれまで災害について深く考えたことはなく、全米の人々がニュースを通して被害の大きさに衝撃を受けたと思います。学生の私も「自分に何かできるのではないか」と感じ、研究を兼ねてニューオーリンズの被災地でボランティア活動に参加しました。この経験をきっかけに、災害と住宅復興について真剣に考えるようになりました。
ボランティア活動を通じて、復興の現場が直面する課題の複雑さを知りました。たとえば政府は危険区域を指定し、「人を住まわせない」との方針を示しました。一見すると合理的に思える判断ですが、実際にはそこで暮らし続けたい住民が立ち退きを迫られる現実がありました。さらに、市の機能が十分に回復していない段階で、新聞に「この地域は将来公園にする」といった「グリーンドット計画」のイメージが掲載され、住民たちは地域が失われることにショックを受け、反対運動を起こしました。そのとき私は、復興政策が住民にとってどれほど切実で身近な問題であるかを理解しました。これらの経験を踏まえ、修士論文では災害後の住宅に関する研究を行いました。
「災害からの復興プロセス」についての研究

日本では、工学部に進まなければ建築学科に進めない場合が多い一方、アメリカなど海外の大学では、芸術分野から建築を学ぶ道も開かれています。私自身も芸術から学びを始め、ワシントン大学と姉妹校である神戸大学に交換留学した際に建築分野へ進みました。その際、1995年に発生した阪神・淡路大震災後の地域復興について学ぶ機会も得ました。
交換留学後は日本の大学で博士課程に進学し、被災地と住宅復興の国際比較の研究を進めました。指導教員の先生のご支援のもと、日本、アメリカ、インドネシアなどの被災地を訪れ、多くの人々の経験を通して住宅復興支援のプロセスを学びました。災害の種類は異なりますが、人々は生活を再建し、社会的なつながりや経済的な安定を取り戻し、家族のニーズを満たす快適な住まいを求めていました。
2011年3月11日、私が神戸大学大学院博士後期課程2年生のときに東日本大震災を経験しました。4月に初めて東北の津波被災地を訪れ、5月には学生ボランティアとして津波被災地の清掃活動に参加しました。この経験をきっかけに、大規模な住宅復興のあり方に注目し、研究テーマを見直しました。被災者の生活をより良くするために、住宅復旧の過程で仮設住宅をどのように転用し拡張できるかに焦点を当てるようになったのです。特に、インドネシアのコミュニティ主導型の住宅復興プログラムに大きな刺激を受けました。2010年のメラピ火山噴火で被災した地域では、専門家やファシリテーターの支援を受けながら、住民が計画から復興に至るまであらゆる段階に主体的に関与しており、その姿勢が私の研究に強い影響を与えました。
私の研究では、災害後の住宅復興やコミュニティの再生、さらには子どもの教育環境の変化などを検討し、それらに対して行政や非営利組織(NPO)などによる制度や仕組みが、どの程度有効であったかを評価しました。支援政策やプログラムは国や災害によって異なりますが、復興の過程で住民が満足し、生活の再建をより良いものにするためには、共通する重要な要素があることに気づきました。それは、「復興のプロセスに十分な選択肢が用意され、住民自身が意思決定できること」です。
私は博士課程の研究において、この考え方を「人間中心の住宅復興」と名付けました。これは、実際に住んでいる人々が復興のあり方を決め、制度が生活実態に即して整備され、住民の声が丁寧に反映されることを意味します。当時は耳慣れない言葉でしたが、近年では「人間中心」という考え方が広く使われるようになりました。私の研究では、復興制度が住民のニーズに合っているか、実際にできあがった住宅や環境に満足しているか、生活の質にどのような変化があったかを検証しました。その結果、「人間中心の住宅復興」を実践すると、住民が自分に合った暮らしを実現でき、満足度が高まることがわかりました。さらに、限られたリソースを有効に活用でき、地域・社会・環境の持続的なつながりを生み出す利点も確認されています。
災害研究のために、東北大学へ

2014年に仙台へ移り、東北大学災害科学国際研究所で勤務を始めました。被災地の研究者や地域住民の方々と協働する機会に恵まれたことに深く感謝しています。
東北の被災地の特徴の一つは、津波被害や原発事故からの復興過程で、追悼公園を含む広大な空き地が生まれたことです。区画整理によって多くの空き地が残され、地域にとって大きな課題となっていました。そこから「空き地をどのように再利用し、人と人とをつなぐ場として活かすか」というプレイスメイキングの研究を始めました。10年にわたりこれらの空間を研究する中で、花や野菜、樹木を育てる活動や、植物のある空間を大切にする取り組みが人々を結びつけることに気づき、グリーン・プレイスメイキングへの関心を深めるようになりました。もともと趣味で畑作をしていたこともあり、イベントづくりにグリーンの要素を取り入れることで、グリーン・プレイスメイキングこそが自分の研究テーマであると確信するようになりました。
近年では、都市農園やファーマーズマーケットなどがもたらす利点についての研究も蓄積されています。これらの取り組みは、人々に直接的な好影響を与えるだけでなく、被災地の復興を支援し、将来の災害に備えた回復力を育む可能性を秘めています。小さな活動であっても、たとえば花を植える、公園を手入れする、コミュニティガーデンで野菜を育てるといった試みが、参加者や地域社会全体に大きな影響をもたらすと考えています。
グリーン・プレイスメイキングの実践!

2020年、友人に誘われて仙台沿岸部・新浜地区のシェア畑「となりの畑プロジェクト」に参加しました。貞山運河の近くに位置するこの地域は、津波によって大きな被害を受けましたが、住民の強い絆がコミュニティ復興を後押しした場所でもあります。
このプロジェクトでは、せんだいメディアテークの支援を得て、地元のアーティストと共に「小屋めぐり」ウォーキングツアーを定期的に開催しました。また、貞山運河とその周辺に息づく文化や生態系の歴史、さらにはカントリーパーク新浜の自然環境や自然農法に焦点を当てた活動として、有機米の栽培をはじめとする生態系教育活動も年間を通じて実施しています。
2023年からは、「小屋めぐり」と並行して、子どもたちも参加できる新しい関連イベント「Welcome Club」を始めました。このイベントでは、地元の食材を使った料理を子どもたちが調理し、来場者に振る舞います。昨年の開催では、子どもたちが農園でハーブや花を収穫し、それらやその他の地元産品を活かして、ローズマリーフォカッチャ、バジルパン、新浜産ポップコーンとハーブソルト、自家農園の黒豆茶など、多彩な料理を作りました。こうした取り組みを通じて、地域の歴史・伝統・文化・生態系・景観、さらにはアートイベントを中心としたさまざまな地域プロジェクトともつながることができました。
これらのプロジェクトと並行して、趣味として新浜で家庭菜園を再開しました。ここ数年、東北でグリーン・プレイスメイキングについて学ぶうちに、菜園活動も実践的アクションリサーチの一環となっていきました。畑では、竹を使った小さな建造物をつくったり、植物同士の相性を活かして共に育てる「コンパニオンプランティング」に挑戦したりしました。プロジェクトメンバーも協力してくれ、近隣の方々から野菜の育て方を多く学ぶことができました。さらに、西洋料理に用いられる多様なハーブを植えたハーブ園を整備し、季節ごとにさまざまな花も育てました。子どもたちが花を摘んだり遊んだりして楽しむ様子を見て、私自身の畑での活動もまた、グリーン・プレイスメイキングの一つになっていると感じました。
そして、2025年から5年間、復興の中のグリーン・プレイスメイキングの役割について、アメリカと日本の研究費をいただけることになりました。ハワイの山火事からの復興について調査し、グリーン・プレイスメイキングが原住民の植物文化や食べ物の文化にどのような影響をもたらしたかを明らかにすることで、被災地間の国際交流に貢献していきたいと考えております。
工学を目指す人へのメッセージ

工学は、ものを作ったりデザインしたりするのが好きな人にとって、とても楽しい分野です。中高生のうちは、やりたいことをひとつに絞らず、趣味や興味の範囲でもいいので、いろいろなことに挑戦してみてほしいです。
建築や都市計画の分野だけでも、建物や屋外・屋内空間のデザイン、素材や技術の研究、人々の暮らしに影響を与えるプロジェクトなど、たくさんのテーマがあります。学んだことは、設計事務所や建設会社、研究の道にもつながりますし、災害リスクを減らす実用的な研究に関わることもできます。
デザインを学ぶことは、アイデアを考え、形にし、試行錯誤して改善していく力を身につけることでもあります。この経験は建築だけでなく、ものづくり全般に役立ちます。ものづくりや空間づくりが好きな人には、建築学はとても楽しい分野だと思います。